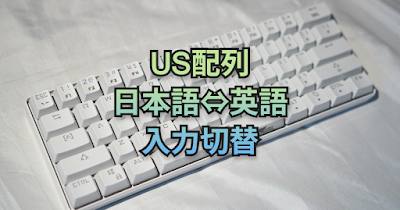Arturia MiniFuse 1&2の実機比較レビュー【高性能なオーディオインターフェース】
Arturia MiniFuse 1と2は、低価格帯でコンパクトかつ音質も良いオーディオインターフェースです。これらの実際の使用感などの比較レビューとなります。
ちなみに、気づいたら2台とも自腹で購入していました。案件では全くありません。(※2台持つ意味は多分無い)
Arturia MiniFuseシリーズの特徴
-
高音質・低ノイズ設計
サンプリングレート/ビットレート:192kHz/24bit
ダイナミックレンジ:110dB
マイクプリアンプゲイン幅:56dB - 48Vファンタム電源やHi-Zスイッチも搭載
- ダイレクトモニター & ループバック機能 (録音・配信時に有用な機能)
- 視認性の高いインジケーター (L/R ボリュームのLED表示)
- 堅牢な金属フレーム (持ち運び時にも安心)
- USBバスパワー駆動 & USBハブ機能搭載 (iPadなどでも動作)
- 独立ヘッドフォンボリューム (スピーカー出力と別々に調整出来て便利)
- MIDI入出力端子装備 (MiniFuse 2と4のみ)
- 価格は1万円台(MiniFuse 1と2)
基本スペックが高い
MiniFuseシリーズの特徴は上記のように比較的低価格で十分な機能を有していて基本性能も高いです。(以下マニアックな解説)
特に音質面では「192kHz/24bit」に対応しているため、高解像度の録音・再生が可能です。(DAWソフトでの設定が必要)
ダイナミックレンジは110dB、THD+N(歪みとノイズの合計値)は-100dBと、同価格帯の製品としては良好な数値であり、クリアな音質です。
マイクプリアンプはゲイン幅56dBと、一般的なコンデンサーマイクからダイナミックマイクまで幅広く対応できます。
さらに、EIN (入力換算ノイズ)が-129dBと非常に低く、マイク入力時のノイズが少ない高品質な録音ができます。
オーディオインターフェースのレビュー自体が日本では少なくて、海外のYouTuberさんの動画を探すと、同価格帯かそれ以上の製品と音質面では差が無いという意見が多かったです。
機能も充実
コンデンサーマイクを接続する際に使う「48Vファンタム電源」やハイインピーダンスの楽器を接続する際の「Hi-Z」スイッチもしっかり完備。
配信等で使える「ループバック機能」はソフトウェアで設定可能で、新しいファームウェア(1.5.0以降)では比較的設定しやすくなっています。
■ループバック機能とは
ループバック機能はPC内部で再生されている音(BGMやゲーム音など)とマイクなどの外部入力の音をミックスして、再びPCへ送り返す機能です。PCの音と自分の声を同時に配信したり、オンライン通話の相手にBGMを流したりできます。
「USBハブ機能」も搭載しているのが興味深く、ここにさらにUSBマイクを挿すことも可能です。(純粋なUSBハブとして動作する)
USBハブ機能はiPadなどとの接続でUSBポートが限られるようば場面で活躍します。
さらに、バスパワー駆動なので電源アダプター不要で取り回しが楽です。一応USB-CポートのあるAndroidスマホでも動作しました。(Redmi note 12 5Gを利用)
バンドル付属ソフトウェア(一部期間限定)
性能面に加えて、付属しているソフトウェアもかなり充実しています。Ableton Liveは世界的に使われているDAWソフトです。
Ableton Live「Lite」は簡易版ですが、初心者には十分な機能が備わっています。そのほか専用のシリアルナンバーが用意されているリストです。
- Ableton Live Lite:作曲・録音・ライブに対応する定番DAW
- Analog Lab Intro:28種のシンセ、500プリセット内蔵
-
Arturia FX(4種):
- Pre 1973(プリアンプ)
- Rev PLATE-140(プレートリバーブ)
- Delay TAPE-201(テープエコー)
- Chorus JUN-6(アナログコーラス)
- Native Instruments GUITAR RIG 6 LE:ギタープロセッシング・ツール
- Auto-Tune Unlimited(3ヶ月):ボーカル補正&エフェクト
- Splice Creator Plan(3ヶ月):数百万のサンプル+チュートリアルへのアクセス
若干気になるLED

|
| MiniFuse 1のLED |
MiniFuseの分かりやすいLEDの点灯なのですが、結構明るくてGAINノブと出力LR部分はチカチカと点滅します。
私の感覚的には正直デスク上に置いてちょっと部屋が暗くなった状態でのLEDは強く感じました。そのため、黒いマスキングテープ(確か100均)を貼って目立たなくしました。
この部分は、環境によって全然気にならない場合もありますし、遠くからでも視認性が良いという利点でもあります。…ソフトで変更出来たら最高ですが…高望みですね。
それと、GAINのクリップが起きるとノブが青から赤へ変わるのですが、ギリギリのラインが分かりづらくて、ここはソフトウェア側に頼ることになりますね。
ここまで、基本的にMiniFuseシリーズすべてに共通した部分でしたが、MiniFuse1と2の違いについて書いていきます。(※MiniFuse 4もありますが値段帯が異なるため今回は割愛します)
Arturia MiniFuse 1とMiniFuse 2の相違点の詳細
デザインの違い
MiniFuse1と2では、大きなデザインの差はありません。純粋に1の方が横幅が5cm短くてコンパクトなだけです。
厳密には機能的に2の方が端子やノブなどが増えるのですが、どちらもシンプルにまとまっていてデスク上でも主張し過ぎないのがいいですね。
私はどちらもブラックモデルを購入したのですが、ホワイトモデルもあって好みに合わせて選べます。
背面から見て異なるのはMIDI入出力があるかないかです。MIDIキーボードなどを接続したい場合にはMiniFuse 2を選ぶのが良いでしょう。※私はMIDI機器を所持していないので動作チェックすらできていなくて申し訳ございません。
Arturia MiniFuse 1 と MiniFuse 2 のスペック比較表
| 項目 | MiniFuse 1 | MiniFuse 2 |
|---|---|---|
| 最大サンプルレート | 192kHz | 192kHz |
| 最大ビットレート | 24bit | 24bit |
| 入力数(フロント) | 1 | 2 |
| Hi-Z対応 | ○ | ○ |
| ファンタム電源(+48V) | ○ | ○ |
| 入力ダイナミックレンジ | 110dB | 110dB |
| 出力数(1/4" TRS) | 2 | 2 |
| ダイレクトモニター | ○ | ○(入力/PC音のミックス可) |
| ヘッドフォン出力(独立レベル) | 1 | 1 |
| MIDI IN/OUT | × | ○ |
| USBハブ | 1 | 1 |
| USBインターフェース | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
| USBバスパワー駆動 | ○ | ○ |
| ループバック機能 | ○ | ○ |
| サイズ(cm) | 15 x 10 x 4 | 20 x 10 x 4 |
| 重量 | 414g | 431g |
スペックは似ているArturia MiniFuse 1とMiniFuse 2の違いについて、より細かく解説します。
入力数の違い
MiniFuse 1:入力=1つのコンボジャック(XLR/ライン)
MiniFuse 2:入力=2つのコンボジャック(XLR/ライン)
入力が2系統あるMiniFuse 2にXLRケーブルなどを繋げた状態はこんな具合です。右にマイクからのXLRケーブルを挿しています。
MiniFuse 2でも奥行きが10cm程度なのでデスクを圧迫せず、XLRケーブルも裏に回せばそこまで目立ちません。
ちなみに右端のヘッドホン出力には3.5mm⇒6.35mm変換プラグを使ってモニターヘッドホンに繋げています。
入力が2つあるとマイク+楽器などを同時に入力できたり、ステレオ入力なども可能になります。
▶XLRケーブル:UGREEN オス-メス XLR キャノンケーブル 2M
▶変換プラグ:3.5mm⇒6.35mm 変換 プラグ RIKSOIN (4個セット)
MIDI接続の有無
MiniFuse 1:MIDIインターフェースなし
MiniFuse 2:MIDIイン/アウトポートあり(MIDIデバイス接続可能)
MiniFuse 2だけにMIDIの入出力端子が搭載されています。
他はどちらも変わらない設計で、OUTPUTSはTRSバランス出力にも対応しています。私はTS×2⇒3.5mmステレオジャックに変換してスピーカーへ繋げています。
使用したケーブル:UGREEN 6.35mm to 3.5mm オーディオ変換ケーブル オス-オス※UGREEN製でなんとなく揃えていますが…大した意味は無いです。
ダイレクトモニタリング機能
MiniFuse 1:ダイレクトモニタリングスイッチのみ(ONでモニタリング音が自動的にモノラルにて再生音とミックスされる)

|
| MiniFuse 2のモニターミックスノブとダイレクトモノスイッチ |
MiniFuse 2:PC音と入力音の調整ノブ(モニターミックスコントロール)とダイレクトモノスイッチで細かな調整が可能
サイズと重量
MiniFuse 1:横幅15 x 奥行10 x 高さ4cm/ 重量414g
MiniFuse 2:横幅20 x 奥行10 x 高さ4cm/ 重量431g
MiniFuse 1の魅力はこのコンパクトさですね。非常に小さくて軽いので、持ち運びにも良いです。もちろんMiniFuse 2でも十分小さいです。
MiniFuse1と2の違いまとめ
■ MiniFuse 1は、1入力のシンプルでコンパクトな設計が特徴で、ポッドキャストやソロ録音に最適。
■ MiniFuse 2は、2入力とMIDI接続にも対応しておりデュエット録音やMIDI機器との連携に便利。
スペック上の違いをまとめてしまえばこんな感じですが、実際に使ってみた感じでは難易度の差もありました。
MiniFuse1と2の操作難易度の差
入力音の扱い方の違い
MiniFuse 1はマイクを接続して各アプリで自動的にモノラル入力となります。
MiniFuse 2では入力1と2で別系統となり、アプリによっては左右どちらかのスピーカー(ヘッドホン)からしか出力されなくなります。(※Windowsのデフォルト録音アプリなど)
それで、MiniFuse 2でモノラル入力を中央に定位させるには、アプリやDAWソフト上で設定が必要となる場合があります。
例えば、バンドルされている「Ableton Live Lite」では入力を1と2から選択できます。(オンライン会議用のZoomアプリでは通常でモノラルだったりします)
ダイレクトモニタリングの仕様の違い
ダイレクトモニタリング機能の違いも結構あり、MiniFuse 1は単純にONにするとPC音は変わらずにマイク音のモニタリングが一定の音量にて出力されます。
MiniFuse 2の場合、モニターミックスコントロールのノブとダイレクトモノスイッチがあり、モニターミックスコントロールを中心に合わせると入力音とPC音が同じくらいのレベルで鳴ります。
そして、ダイレクトモノスイッチを押すことで、1つだけの入力でもモノラル音として中央に音が定位するようになります。
MiniFuse 2で感じる大きな違いはモニターミックスの部分で、PC音だけ(右に回し切った状態)から少しでも左に回していくと、常にダイレクトモニタリング状態になります。
そのため、モニターミックスノブを中央にしたままだと、マイク入力を1にしていると左からだけモニタリング音が聞こえた状態となります。
そして、ダイレクトモノスイッチは入力音をステレオかモノラルに変更するだけの機能です。

|
| ダイレクトモニタリング中間・モノラル出力の状態(光を弱めるマスキングが…) |
この利点は入力1(左から出力)と入力2(右から出力)をバラバラに分けるか、モノラルにして全て中央でモニタリングするかも決められることです。
ただ、この仕様を理解していないと常時モニタリング状態(モニターミックスノブが左に少しでも回っている場合)になっている場合があるのです。

|
| ダイレクトモニタリングOFF・PC音のみの状態 |
これは慣れが必要ですね。モニタリングしないならモニターミックスノブは常に右に回し切っている必要があります。(※私はどうなっているのか理解するのに結構時間がかかりました)
ちなみにMiniFuse 1ではダイレクトモノスイッチだけでON・OFFというシンプルな設計なので迷うことはほぼ無いです。
MiniFuse 2にて、モニターミックスノブとダイレクトモノスイッチを上手く組み合わせることで適切なダイレクトモニタリングが可能になるということでもあります。
ザックリまとめると、MiniFuse 1はダイレクトモニタリング時のPC音と入力音のバランスはPC側でしかできないけれど、ボタン一つで簡単にON・OFF可能。
MiniFuse 2はモニターミックスコントロールノブとダイレクトモノスイッチを使って本体だけでPC音と入力音を調整可能だけど、操作が複雑。
という感じですが、言葉での説明だと本当に伝わりづらいですね。
操作難易度の違いまとめ
- 初のオーディオインターフェースでマイクや楽器1つだけ使うならMiniFuse 1がおすすめ
- オーディオインターフェースの扱いに慣れた人や楽器とマイクなど2系統の入力が必要なら2がおすすめ
こんな具合です。ただ、MiniFuse 2の価格が割安な場合(MiniFuse 1とあまり差が無い)には将来性も考えてMiniFuse 2がを選ぶのが良いかと感じます。
各ユーザーマニュアル
- MiniFuse 1:https://dl.arturia.net/products/minifuse-1/manual/minifuse-1_Manual_1_0_0_JP.pdf
- MiniFuse 2:https://dl.arturia.net/products/minifuse-2/manual/minifuse-2_Manual_1_0_0_JP.pdf
まとめ
MiniFuseシリーズは基本スペックのしっかりしたオーディオインターフェースで、録音環境をすぐに整えられる充実のソフト付きパッケージです。
ただ、初心者にもおすすめかというと若干設定が難しいですね。noteにて初期セットアップやループバックについてまとめています。(こっちの方が長いです)

Arturia MiniFuse 1&2 初期設定からループバック設定までの解説|参考サイトの管理人
日本でオーディオインターフェースといえば「YAMAHA AG03 Mk2」が有名で情報も多くて扱いやすいです。 そんな中、私は性能&コスパ重視で「Arturia MiniFuse」シリーズのオーディオインターフェースを選んでみました。(1と2なぜかどっちも買いました) がしかし… 初期設定は結構時間がかかり、ループバックの方法に関しては最新の情報がほぼなく、私もDTMは全くの初心者… そのため、手探りで設定を試してループバックに関しては「恐らく合っている」レベルとなります、ご了承ください。 Arturia MiniFuse 1&2の初期設定 本体(MiniFuse 1)
どちらのモデルも購入して実際にいろいろ試したのですが、どちらにも良さがあってシンプルさはMiniFuse 1、さらに本格的な仕様なMiniFuse 2となっています。
個人的にはMiniFuse 1も2も基本性能は高く、好みや用途に応じて選べばどちらも満足できる製品だと感じますね。
価格が近ければ(もしくは予算的に問題なければ)拡張性の高いMiniFuse 2が良いですね。操作に慣れてしまえば多くの用途に対応できます。