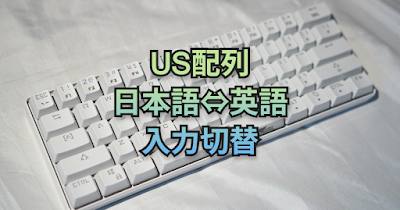【実機レビュー】FIFINE AmpliTank K688は初心者にもおすすめ?マイクアームとの併用は必須
「FIFINE Ampligame A8」USBコンデンサーマイクのデザインや音質にも満足していましたが、音響機器好きとして他の方のレビューを見て気になっていた「FIFINE AmpliTank K688」にも手を出してしまいました。
この記事では、実際に使って分かったK688の音質・使い勝手・初心者へのおすすめ度などを詳しく解説します。
FIFINE AmpliTank K688の利点と気になった点
FIFINE AmpliTank K688を実際に使ってみてのメリットとデメリットをざっくりとまとめます。
利点
- 実売約10,000円で高音質
- USBとXLRの両対応
- USB接続にてダイレクトモニタリング可能
- 単一指向性で環境ノイズを抑制
- シンプルで馴染みやすいデザイン
気になった点
- マイクスタンド・アームが別売
- 背面ノブがあまり直感的でない
- マイク感度が低く音量が小さいと感じるかもしれない
- XLR接続ではそれなりのゲイン幅が要求される
以上のような点が実際に使っていて感じられました。
k688は初心者におすすめできるか
結論から言うと、初心者でも使えますが準備とセッティングの難易度は少し高めです。
USB接続ができるがスタンドが別売
K688はUSB接続が可能である点は初心者にも扱いやすいと感じました。
しかし、オールインワンでUSBを挿してすぐに使えるかというとそうではなく、別売のマイクスタンドかアームを用意する必要があります。
別途マイクスタンドやアームを用意する場合(マイクアーム付きモデルもある)結局合計で15,000~20,000円くらいの出費になります。
マイクセッティング難易度は少し高い
K688はダイナミックマイクで感度は低めなため、USB接続でもXLR接続でも音量を稼ぐのが難しいです。
ダイナミックマイクはこぶし1個分・約5~10cmの近距離で使うのが基本になります。(マイクの正面から声を入れる必要もある)
適切な位置を保つセッティングのためには、マイクアームが重要になるわけです。
この際にデスクのどこに取り付けて、どのように取りまわすのかをイメージしておく必要があります。
感度の低いダイナミックマイクとキーボードやマウスを一緒に使うためには、適切なマイク位置を保つことができ、不要な際には動かしやすいアームを使うのが良いです。
個人的には同じFIFINE製ロープロファイルマイクアームと一緒に購入するのがベターだと感じます。安価なスプリング式の物と比べて快適性が違います。

FIFINE BM88 ロープロファイル マイクアームのレビュー|参考サイトの管理人
今回は、FIFINE K688というダイナミックマイク用に合う、同じくFIFINEのBM88マイクアームのレビューをしていきます。(※筆者はなぜ音響機器に拘り始めたのか自分でもわかっていません) FIFINE BM88の製品概要 FIFINE BM88は配信や録音のために設計された、扱いやすいロープロファイルマイクアームです。 耐久性のある金属製フレームと、滑らかな動きと、調整可能な関節が特徴です。 主な仕様 素材:アルミ合金(主要パーツ)・プラスチック(一部カバーなど) 対応マイク重量(耐荷重):約1.5kg アーム長さ:合計約70cm(アーム約30cm x
安価なUSBコンデンサーマイクより使用難易度は高いがスペックも高い
K688はより安価でスタンドも付いたUSBコンデンサーマイクよりも扱いが難しい面があります。
FIFINE AmpliGame A8のようなコンデンサーマイクの場合、30cmくらい離しても音を拾います。(逆に環境音を拾い過ぎる欠点はありますが)
AmpliGame A8のレビューも行っています。こちらも手軽に高音質な環境を整えるのに良いマイクです。

FIFINE AmpliGame A8 いまさらレビュー【デザインだけでなく音質も良い】 - plz-reference-blog
FIFINE AmpliGame A8をいまさらレビューしてみました。RGBの美しいライティングに加えて見た目だけではない性能の高さもなかなかのものでしたね。
設置自由度の高いUSBコンデンサーマイクと比べ、K688などのダイナミックマイクは導入時に考える要素が増えます。
個人的には初心者に安易にはおすすめできないけれど、総合的なスペックや品質の高さがあるので、用途次第で確実にメリットのある製品です。
特に今度オーディオインターフェースの導入も視野に入れている場合、XLR接続に対応したK688の拡張性は強みです。
オーディオインターフェース導入のメリット
私は現在Arturia MiniFuseというオーディオインターフェースをK688とXLRケーブルで接続して使用しています。…流れで買ってしまったんです。

Arturia MiniFuse 1&2の実機比較レビュー【高性能なオーディオインターフェース】 - plz-reference-blog
Arturia MiniFuse 1と2という低価格で高品質なオーディオインターフェースの実際の使用感を詳細にレビューしました。
実際に使ってみた具体的なオーディオインターフェースのメリットを考えてみます。
拡張性と接続の自由度が広がる
オーディオインターフェースは、マイク以外にもギターやキーボードなどの楽器、外部エフェクター、モニタースピーカーなどを接続できます。
将来的に複数マイクでの収録や配信、音楽制作に挑戦する場合でも、そのまま使い回せるのが大きなメリットです。
配信や録音での遅延(レイテンシ)を低減できる
PC内蔵のオーディオ機能に比べ、インターフェースを使うと遅延(レイテンシ)を減らすことが可能な場合が多いです。
ゲーム実況やライブ配信でも声と映像のズレを最小限に抑えられ、さらにダイレクトモニタリング機能で自分の声をリアルタイムで確認できます。
音作りの幅が広がる
EQ(音質調整)コンプレッサー(音圧調整)リバーブ(残響)などをリアルタイムで適用できる機種もあります。
これにより、録音段階で完成度の高い音を作り込むことができたり、配信時のバリエーションを増やせたりします。
音質が向上する(場合がある)
オーディオインターフェースを導入すると、K688のUSB接続時のスペックである16ビット/48kHzを超えた録音が可能になります。(対応するオーディオインターフェースが必要)
USB直接接続に比べて音の細部がしっかり再現され、ダイナミックレンジも広がる場合があります。(もちろん選ぶ機器によります)
注意点
K688はマイク感度が比較的低いためオーディオインターフェースに最低でも50dB以上のゲインが供給できる必要があります。
また、マイクプリアンプの性能面でもゲインを上げてもノイズが少ないモデルを選ぶのが良いでしょう。
高品質なプリアンプを搭載したモデルなら、ゲインを上げてもホワイトノイズがほとんど発生しません。
私がK688を選んだ理由【SHURE SM7Bとの比較動画】
YouTube上では、K688がSHURE SM7Bに迫る音質とのレビューがありました。
▼SHURE SM7Bとは
SHURE SM7Bは、価格が約5〜6万円前後のプロ向けマイクです。アナウンサーや声優、プロの歌手、有名配信者など、クリアかつ耳に心地よい音質を求める人に愛用されています。
正直、K688購入の決め手になったのはYouTubeにあったSM7Bとの比較動画でした。海外のYouTuberの方ですが、貴重な比較動画に感謝です。
YouTubeでの音声比較になるので限界はあるのですが、YouTubeで違いが分からないとしたら…プロレベルの収録以外でこれ以上のスペックが必要なのか?
私はオーディオテクニカのモニターヘッドホンで何度も聞きましたが、ほとんど大差ないと感じませんでした。
他のレビューもいろいろ見たのですが、最終的にデザイン・性能・価格のバランスでFIFINE AmpliTank K688を選びました。
もちろん違う意見があるとも思いますので参考程度でお願いします。
FIFINE AmpliTank K688の詳細スペック
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 型式・指向性 | ダイナミック型・単一指向性(カーディオイド) |
| 周波数特性 | 70 Hz–15 kHz |
| ビット深度 / サンプリングレート | 16ビット / 44.1–48 kHz(USB接続時) |
| 感度 | −58 ± 3 dB |
| 最大音圧レベル SPL | 130 dB |
| ゲイン調整範囲 | 0 ~ +12 dB |
| S/N比 | > 75 dB |
| 重量 | 約320 g |
| 接続方式 | USB・XLR 両対応 |
基本的な音質の方向性
K688はダイナミック型らしい音質ですが、低音の盛り上がりは自然でこもり感が少なく、近接効果も控えめです。
周囲ノイズやキーボード音を抑え、芯のある声を録音できますね。
USB接続時の音質
K688をUSBでPCに接続すると、Windows上では「fifine-Microphone」として認識されます。このときの最大スペックは16ビット/48kHzです。
これはCD音源と同等、またはわずかに上回るレベルで一般的なボイスチャットや配信、ナレーション録音には十分です。ノイズが少なく、温かみのある音質が得られます。
ただし、プロのレコーディングなど、音の細部までこだわりたい場合は、わずかながら表現力に限界を感じるかもしれません。(オーディオテクニカのモニターヘッドフォンで注意深く聴くとわかる程度)
XLR接続時の音質
XLR接続時には、K688はオーディオインターフェース(Arturia MiniFuse 1)を介してPCに繋なげました。
24ビット/48kHzとなり、USB接続時よりもデータの情報量が増えます。※ここでの差はほぼわかりません。
音質的には、USB接続時と基本的な傾向は変わりませんが、より細かな音のニュアンスまでしっかり拾ってくれる印象です。
ゲイン最大でも小さいと感じる場合、マイク位置やインターフェース側の設定を見直す必要があるかもしれません。
サイレントアップデートに関して(2023年)
K688は2023年に内部設計がひっそり改良されたようです。
- ダイヤフラム位置を奥に変更
- USBケーブルの品質向上
- ポップフィルター強化による破裂音軽減
- 近接効果(低音の盛り上がり)が緩やかに
※詳しくは海外のYouTuber Dave Soltura さんの解説動画があります。 (https://youtu.be/FtlKBp251GM?si=3K4pCyIsV0y7RqSS)
デザインと機能面
シンプルで癖のない外観
マット仕上げの筐体は派手なRGBを排し、ブラックとホワイトの2色展開。私は落ち着いた印象のブラックを選びました。
ショックマウント&ポップフィルター標準装備
衝撃ノイズを抑えるショックマウントと、破裂音を軽減するポップフィルターが付属。ポップフィルターは灰色のモフモフ部分です。
USB接続時の操作性
USB-Cでの接続なら、PCやゲーム機に直接接続が可能です。付属のUSB-Cケーブルで繋げます。
背面ノブでゲイン・モニタ音量調整
ノブの配置が直感的でないため、最初は慣れが必要です。(USB接続時のみ利用可能)
ダイレクトモニタリング可能
遅延なく自分の声とPC音を確認可能です。初回は小音量から調整するようにすると安全です。
タッチ式ミュートボタン
上面のセンサーで静音化。LED表示で状態が分かります。緑色点灯がONで赤がミュートです。(USB接続時のみ使用可能)
XLR接続での操作性
XLR端子を使った接続では、オーディオインターフェース経由でPCに繋ぎます。XLRケーブルも別売なのは注意点ですね。
ちなみにUSBとXLRは同時接続も可能で、機器ごとの使い分けや同時録音もできます。
まとめ

FIFINE AmpliTank K688は 「USBで手軽に、XLRで本格的に」を両立した高コスパなダイナミックマイクです。
正直、初心者には手放しでおすすめできるわけではありませんが、用途次第では確実に選択肢に入ります。
防音環境が整っていない家庭録音でも安定して録音でき、後から機材を追加できる拡張性があるのも魅力ですね。
一緒に使うマイクアームは同じFIFINE BM88がデザインや機能的にもおすすめです。